前回に引き続き、「ありがとう」についてのブログであります。
前のブログでは、凡の情緒的な、ありがとうという言葉についての雑談でありましたが、今回は、偶然に見つけた八幡書店さんの武田嵩元さんのユーチューブで語られていました「『ありがとう』に言霊なし」というテーマについてご紹介がてら、これまた独り言を呟いてみたいと思います。
前も書いたのですが、武田さんがユーチューブで発信するなんて、ひょっとして、新しもの好きの目立ちたがり屋さんだったのだろうか。
素直にビックリであります。
でも、このユーチューブを見ている人は、かなりのマニアックな人だけに違いない。
何しろ、おっちゃんが、上から目線的な喋り方で、持論を語るだけの動画なんですもの。
まあ、これを見てる人は、八幡書店のファンであることだけは、容易に推測できるわけであります。
それを、凡も見ている訳なんですけれどね。
ここで、これを読まれている人は、たぶん八幡書店と聞いてもピンとこないと思いますので、ちょっとだけ、八幡書店さんのご紹介を。
八幡書店さんは、神道、仏教、まじない、占術、仙道、などなど、精神世界全般に関する本を出されている出版社だ。
古い文献などを復刻したり、他では、なかなか手に入らない本などがあって、不思議大好き凡には、とても魅力的な出版社というか、本を取り揃えておられる。
それで、この八幡書店さんで、何が楽しいかと言うと、定期的にパンフレットが届けられるのですが、それを読むのが楽しいんです。
普通の書店には置いてないような本が紹介されていて、その説明文を読むのがおもしろい。
たぶん、その1部は、社長の武田さんが書いているのではないかと思われる文章。
これまた、断定と上から目線の宣伝。
ただ、この上から目線が、最近のパンフレットは、かなりソフトになってしまっているので、ファンとしては、それが逆に残念なのではある。
他の人には書けない宣伝コピーなので、また過激なコピーになることを期待しているのであります。
そして、その社長というのが、何回も書いている武田嵩元さんなのである。
さて、「『ありがとう』に言霊なし」というユーチューブの話であります。
言霊というものは、なかなか難しいものである。
なので、凡には説明が出来ない。
そうだ、参考にしようと思って、昔買った八幡書店の「言霊研究入門」(小寺小次郎著)を出してきて、パラパラと眺めてみたが、まだ読んではいない。
なんや、まだ読んでないんかーいとツッコミを入れられるかもしれませんが、何しろノロマな凡でありまして、本を手に取っても、また読むのが億劫になっているのではあります。
んでもって、言霊についてなんだけれど。
言霊と言っても、いくつかの捉え方があって、研究する人によって、違った側面からアプローチしている。
音に基本を置く言霊。
例えば、「あ」とか「う」とか、そんな、ひとつの音の観点から考察する方法。
これは、なかなか意味の深いものでありまして、その音をどう解釈するかっていう本もでてはいるけれども、凡には難しすぎて、読んでもチンプンカンプンだ。
出口王仁三郎も、霊反し(たまがえし)と言って、複数の音が組み合わさった言葉を、わざわざ、1つの音に集約させて、その本質を探るなんてことをされている。
なかなか、難解ではありますが、興味深いものでもあります。
また、音を組み合わせた言葉としての言霊。
その中でも、2つあって、1つは、その言葉自体には、神秘な力をもっているが、意味の不明な言葉。
例えば、「ヒフミヨイムナヤコト」とか、神道なんかで唱えられたりするもの。
んでもって、もう1つは、聞いて意味の分かる言葉。
武田さんは、言霊じゃないと力説されていますが、「ありがとう」とかね。
また、小泉太志さんの「ととのう」というのが、それでもあります。
「ととのう」も、ありがとうと同じで、言霊じゃなくて、普通の言葉だとも解釈できなくはないのですが、小泉太志さんが、この言葉を言霊としてよく使っておられたそうだから、そこは、言霊なんだろう。
んでもって、その延長にある、もっと長い言葉の組み合わせ。
その例が、歌だ。
短歌だったり、或いは、みゆきさんの作った歌とかね。
昔の話で、災いが迫ってきた時に、短歌を詠むことで、その災いを消してしまったりね。
みゆきさんの歌だって、これは、武田さんも、また、ほとんどの人が否定するかもしれないけれど、あれも言霊なんだよ。
どんなに疲れていても、みゆきさんの歌を聴いたら、スッと軽くなる。
だから、いつの時代も、みんなが聴きたいと思うんだよね。
んでもって、これは誰か言っている人がいるのだろうか。
凡が、考えたオリジナルじゃないかと思うのだが、どうなんだろうと気になる言霊がある。
それは、人間の口、喉を通じて、音を発せられる前の、音になっていない音の言霊だ。
凡の目の前に可愛い女の子がいる。
凡は、その女の子の目を見て、そしてウインクをする。
大概の女性は、凡のイヤラシイ目のウインクでイチコロだ。
すると、女の子は、何とも言えない快感に襲われて、「あん。」と思わず声を漏らしてしまう。
いや、「あん。」とは声に出さずに、ただ、息だけがもれる音。
声にならない、声帯を使わない声。
それも言霊なのかもしれない。
でも、凡の言いたいのは、それじゃない。
それよりももっと前の段階で、さらに、無意識ではなく、意識のある状態での、声になる前の声のことだ。
凡は、無意識ではなく、ちゃんと意識をして声を発しようとした瞬間の、その前の状態の、声になっていない声の言霊があるんじゃないかと思うのです。
何かの言葉を発しようと思った瞬間、その思ったのは脳なのか、或いは、魂なのかが、イメージで発する言葉を組み立てた時の言霊。
まだ、音にはなっていないが、思考の中に波動として発生した言葉の音。
それもまた、言霊ではないだろうか。
何故、それが言霊かというと、人間は、言葉に依って思考する生き物である。
何かを考えたりするときに、頭の中で、言葉で考えている。
これは、人間特有の現象ではないだろうか。
でも、これがあるから人間は発達してくることができたとも言える。
何故、頭の中で、言葉を使って思考するのかというと。
言葉を発することが出来る口と喉を持っているから、言葉で考えるのじゃないだろうか。
だから、ここまで発達した社会を作ることが出来た。
同じような遺伝子を持つオランウータンは、言葉を発するようには口の周りの器官が出来ていないので、言葉で考えることをしていないのではないだろうか。
ただ、情緒と本能だけで行動している。
でも、人間は、言葉で思考するので、何かを発しようとすると、まず、頭の中で言葉を組み立てる。
頭の中で、組み立てられた言葉は、それは既に言葉であるから、たとえ、口から発せられずとも、こころの声で発しているから、言霊として活動を始めるのではないだろうか。
頭の中で、言葉で何かを考えた瞬間、それが言霊になる。
そう思うと、ただ単に、頭の中で考えていると思っていることが、実際に言霊を発した時のような結果を生むかもしれないのだ。
そう考えると、よほど、心を美しく清らなものにしないと、エライことになるよ。
凡なんて、いつも邪悪な事や、エッチなことも、、、たまにはね、頭の中で妄想したりする。
そんな妄想も、これまた言霊だってことになったら、どんな影響が出るのかと思ったらゾッとするね。
くれぐれも、心を清くして、生活しなきゃね。
と言う事で、この言葉になる前の言霊については、誰か言霊に詳しい人がいたならば、ご教示頂きたいものなのであります。
ということで、言霊についての説明が長くなってしまいましたが、この説明も、合っているかどうか、自信がありません。
もし、興味のある方は、他の言霊について解説されている方に、聞いてみてください。
んでもって、始めのユーチューブの「『ありがとう』に言霊なし」なのであります。
武田さんは、ユーチューブの中で、ありがとうを何回も唱えると幸せになりますとか、願いが叶いますということをやっている人は、「ありがとう中毒」だと説明しています。
そして、そんなことをするのは「性根があさましい」とまで言ってバカにしてらっしゃいます。
すごいね。
でも、その気持ちは、凡も解る気がするんですよね。
前回のブログで、凡の情緒的な、ありがとうに対しての感想を書いたのですが、その時に、ギブ・アンド・テイクの要素があるから嫌いだと書いたのでありますが、武田さんの性根があさましいに通じるところじゃないかと思う。
何か、良いことを、何か、ラッキーを貰うために、ありがとうと唱える。
それって、ギブ・アンド・テイクと同じじゃないかな。
まだ貰っていないラッキーを将来テイクするために、ギブをする。
ラッキーなことが欲しいから、先に、ありがとうって言っておこうみたいな。
でも、果たして、このありがとうを唱える開運法は、効果があるのだろうか。
ということで、ユーチューブの内容について、もっと書こうかと思っていたのですが、それについては、凡が書くよりも、興味のある方は、実際のユーチューブを見て頂いた方が間違いないので、ここにリンクだけ貼っておこうかなとおもう。
武田嵩元さんの「『ありがとう』に、言霊なし」はこちらから⇒⇒⇒
リンクが切れていたりしたら、ごめんなさい。
(勝手にリンクさせて頂いております。武田さん、ゴメンナサイ。)
今回のブログは、最後は、尻切れトンボみたいになってしまって、ゴメンナサイ。
んでもって、八幡書店さんのホームページは、こちらから⇒⇒⇒
と、八幡書店さんの宣伝みたいなことを書いておりますが、ファンとして書いているだけで、アフェリエイトなどとは関係ありません。
ということで、早く次のパンフレット届かないかなあ。
今回も、ぐだぐだで、尻切れトンボのブログになってしまいましたが、最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございます。

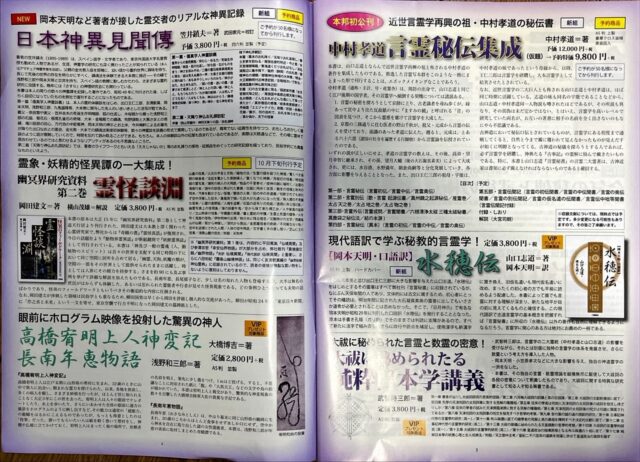
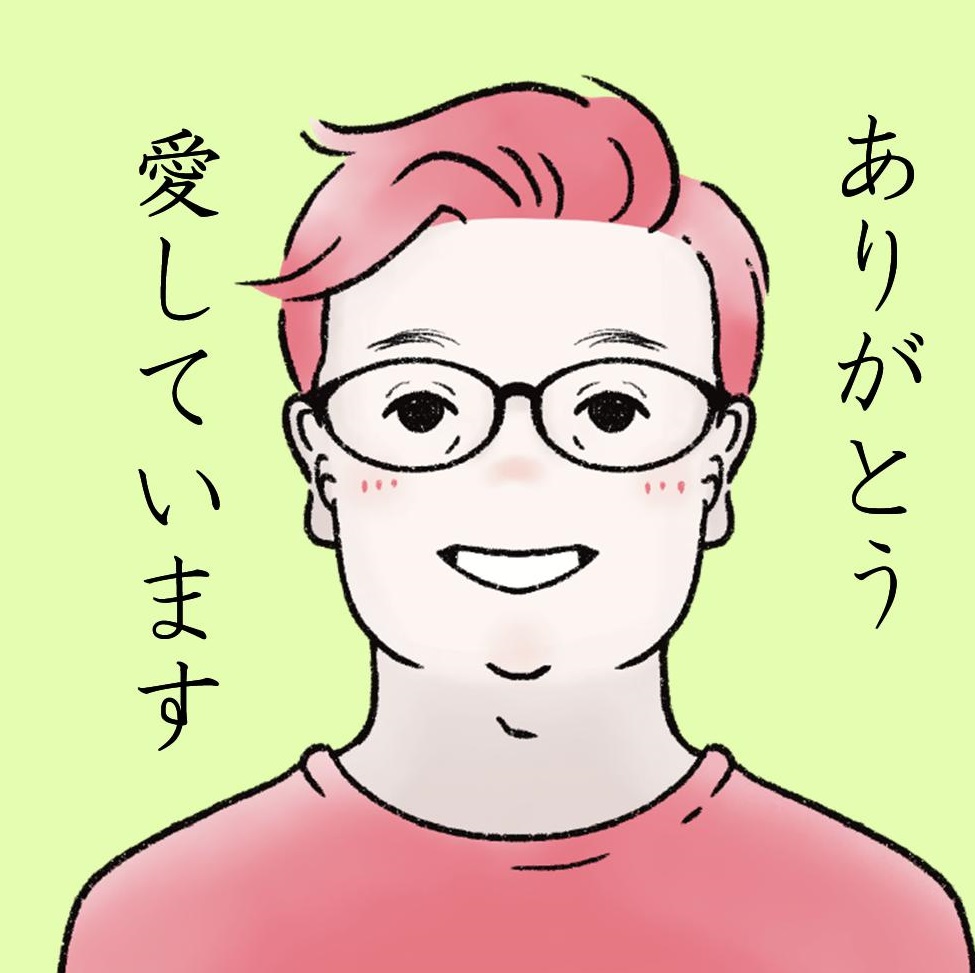
コメント